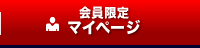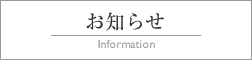Master's Perspective
高分子工学と医学・生物学の学際研究として肝細胞研究を志して50年‼️
赤池敏宏(東京工業大学名誉教授)
筆者は東京大学工学部で高分子合成化学を専攻(1975年博士)修了後に、東京女子医大・日本心臓血圧研究所・理論外科という珍しい名前を有する医工連携を目的とする部門に助手として採用された。私の入室する数年前に前に心臓外科教授として有名な榊原仟(しげる)先生によって新設されたばかりであった。東大で渥美和彦教授と精力的に人工心臓開発を推進されていた櫻井靖久助教授を榊原仟(しげる)先生が後継者として指名されたそうであった。新天地で櫻井先生はたいへん張り切っておられた。さて私自身は生まれて初めて解剖学、病理学、生理学等々の医学の各分野を勉強しながら高分子工学の医学・生物学への応用展開を図った。恩師の故鶴田禎二教授(工学・東大)と故桜井靖久教授(医学・心臓外科/東京女子医大)のお二人が願望されていた"医療福祉に貢献するバイオマテリアル・サイエンス(材料生化学)"なる分野をできるだけ早く具体的にスタートさせ世界に発信・アピールすることをめざした。その結果としてこのバイオマテリアルサイエンスという新分野は50余年が経過した今やなかなかのオリジナルな分野として発展している。片岡一則氏(現在東大名誉教授)、岡野光夫氏(現在東京女子医大名誉教授)のお二人は筆者がこの当時未開拓の分野と言われていた工学と医学・生物学の学際領域としてのバイオマテリアルの開拓事業にいわば最初にチャレンジし"夜明け"を闘い抜いた同志であった。多少の偶然も重なるがスタート後5年余りを経過する頃からそれぞれの興味を発展させ三者三様の道を歩み始め、さらにユニークなバイオマテリアル研究の発展に邁進した。私が東京農工大、東京工業大さらにはつくばでの小研究所に至るまで掲げ続けた生涯研究のテーマ「細胞認識性バイオマテリアルの設計と開発」は、東京女子医大で医学・生物学・高分子工学分野間の橋を渡りつつ少しずつ醸成していったものでもある。さてさて1985年にその理論外科においてたった助手定員1名でスタートしたバイオマテリアル研究グループ(4年後岡野・片岡両氏の博士課程修了を待って3人助手体制)は次の世代の若い優れた研究者たちの活躍も相俟って今では第三世代、一部に第四世代にまで突入している。ざっと数百人が日本全国各地の、いや世界各地の大学・研究所,企業等のアカデミア,研究部門,生産部門に分散し、それぞれにおいて教授、准教授、助教、研究員等としてバイオマテリアルに関する研究教育活動に従事していることになる。私達仲間が夢と描き・実現を目指したバイオマテリアルの明治維新はこのような経過を経て実現できたといっても良いだろう。
筆者自身は東京女子医大での5年間(1975-1980)の多少苦しくも、楽しく充実した学際領域バイオマテリアル分野開拓事業に従事して後、少し離れた小金井市にある東京農工大学工学部に、おそらくはわが国で初めての工学部内にできた医用高分子研究室(半講座)助教授として移動した。
実は動物実験は不可とされていたこの時期から意を決し、なけなしの予算で初めて細胞培養のインキュベーターを購入し各種の合成高分子、ポリペプチド、タンパク質系マトリックスの評価システム立ち上げを開始した。各種の株化細胞の培養を中心に、そしてやがては動物実験の許可をいただき、初代培養肝細胞と新規開発されたマトリックス材料との相互作用解析にシフトしていった。そして医療に応用するバイオマテリアルの設計論として有機化学者Breslow教授(米国コロンビア大)その当時提唱されていたBiomimetic化学のコンセプトを取り入れることにした。こうして生体内でおこなわれている細胞・マトリックス間あるいは細胞・細胞間の認識反応を、単純化したオリゴ糖やペプチドを取り込んで設計した"バイオマテリアル"と細胞との相互作用で置き換えてみることにした。(筆者達のいわゆる"糖鎖マトリックス工学"と"カドヘリンマトリックス工学"のスタートであった。)当時名古屋大学の助手だった小林一清先生(現在、名古屋大学名誉教授)との劇的な出会いと信頼感に結ばれた共同研究によって私達の"細胞認識性バイオマテリアル"の医療応用・糖鎖工学的設計論は長年にわたって進展していった。
その頃の強烈な思い出の苦労談を一つ!折から医学・生物学の専門家達で活動開始された"初代培養肝細胞研究会"(徳島大学附属施設施設長の市原明教授が大塚製薬の全面的御支援で設立)には結成されるとすぐ参加した。細胞生物学者、肝臓の病理学者、内科医・外科医の集まりではあったが唯一人の工学系研究者として勇猛果敢に参加・入会し、第一回から毎回連続参加した。が、周りは無関心!発表はほとんど無視され続けた。"コラーゲン(C)やフィブロネクチン(FN)上では全く実現しない肝細胞の分化機能の持続的な維持が私・小林先生の合作であるラクトース側鎖を有するスチレンの重合体コート表面では唯一可能となることを報告し続けたのである。(研究をギブアップしなくてほんとうに良かった‼️が今の我々の本音実感‼️である。)
採ったばかりのいわゆる初代培養肝臓細胞を培養する技術を立ち上げて当時世界中で開発・発見競争のまっただ中にあった肝細胞増殖因子(HGF)を探す実験だけが注目され続けた時代であった。それで肝細胞研究は十分だという雰囲気の主流の中で我々が偶然見つけた肝細胞だけが選択的に接着する新しいコーティング材料の発見という発表は無視されることが多かった。そういう中から肝実質細胞はきわめて選択的にラクトース(末端がガラトース)側鎖型のポリスチレン(PVLAと略称)に効率的に接着し、肝硬変に関わる星細胞とりわけ活性化した星細胞はキトビオース(末端がN-アセチルグルコサミン)側鎖型ポリスチレンを極めて特異的かつ効率的に認識して接着・長期生存したのである。PVLAはポリスチレンのような数多くの疎水性材料表面にはきわめて安定にモノレイアー吸着するので既存の疎水性シャーレ上にこのコーティング処理すると驚いたことには肝細胞以外の細胞はまったく付着しなかった。もちろん血液中のいかなる細胞も接着せず、別の観点から言えばきわめて優れた"抗血栓性材料"でもあった。(これらを皮切りに現在の主力テーマでもあるカドヘリンマトリックス工学系のバイオマテリアルの設計にまで次々に進展していくのであったが余り長くもご紹介できないのでその後の開発物語が前述のPVLA開拓物語に連なっていることだけを強調して筆を置く。)
PVLA物語の数奇な展開!。その1。PVLA上に選択的に接着生存した肝実質細胞はその表面上に多数存在するガラクトース認識レセプターに媒介され活発にに動き回り、数時間程度で自発的に肝細胞スフェロイドを形成!!長期にわたりスフェロイドを維持するこの肝細胞集団はほとんどミニ肝臓状態であった。!!!(1980代後半)他の細胞を混合することも可能であった。(今をときめく肝臓オルガノイド研究の始まりであったともいえる。)余りに分化維持性能が良いのでスフェロイドの維持機構を解析すると、所々に形成される毛細胆管部を含めてほとんどすべての肝細胞間がEカドヘリンで媒介されて接着し肝細胞としての各種の分化機能を発生維持していたのであった。誠に合理的な説明が可能となった。ここからE-カドヘリンのキメラ抗体分子化によるマトリックス化へのチャレンジが開始されたのである。この発見から長岡正人博士他のたくさんの東京工業大学の学生が続々参加しての分化機能維持用のコーテイング材料の設計開発!それ以後のES,iPS等各種幹細胞の世界初のシングル細胞維持型未分化増殖系培養法の確立につながっていった。(その詳細は各オリジナル論文他たとえば日本再生医療学会誌の2012年11月号の解説と2020年11月号掲載の日本再生医療功績賞論文をご参照下ください!)
こうして現在に至るまでに〝細胞認識性バイオマテリアル設計″の考えを徐々に確立していくことができた。高分子合成化学(筆者の場合は糖質高分子・ペプチドの科学がベース)に基づくバイオマテリアルからスタートして遺伝子工学(同じく私たちの場合はカドヘリン・サイトカイン分子の細胞分子生物学がベース)に基づくバイオマテリアル設計を展開出来たかと思う。今ではいずれも、バイオ(ハイブリッド)人工臓器やES/iPS細胞を筆頭とする各種幹細胞を利用する再生医療を支える重要なマトリックス(足場材料)として応用することができる。この分野での医学と工学を融合させる作業は筆者の場合は試行錯誤の連続で40余年かかったのであった。このプロセスは本学会の歴史と重なっていると言っても過言ではないでしょう!
私は本年7月で78歳となった訳であるがこの五年余のつくば市での研究室経営をへて今もなお肝細胞・ES細胞を対象として細胞認識性バイオマテリアルの医療応用・特にカドヘリンマトリックス工学・糖鎖工学の実用化を目指す研究を続けている。第1回大会を主催させて頂いて以来、この度母校東京大学にて酒井教授主催で開催される第31回に参加させて頂き嬉しい限りである。
参考文献
- 2020 年度日本再生医療学会功績賞: 赤池 敏宏. 細胞認識・機能制御性バイオマテリアルの設計・開発と再生医療・医工学への応用. 日本再生医療学会雑誌. Vol.19 No.4 p.1-8.
- 赤池 敏宏. 医療の向上に貢献する細胞認識性バイオマテリアル開発とその課題─ 人工臓器用生体適合性材料から再生医療用のES/iPS細胞用まな板をめざして ―學士會会報 №915(2015-Ⅵ).
- Haque MA, Nagaoka M, Hexig B, Akaike T. Artificial extracellular matrix for embryonic stem cell cultures: a new frontier of nanobiomaterials. Sci Technol Adv Mater. 2010 Feb 26;11(1):014106. doi: 10.1088/1468-6996/11/1/014106.
- 赤池 敏宏, 長岡 正人. 細胞認識性バイオマテリアル設計からカドヘリンマトリックス工学を展望して. 日本再生医療学会雑誌 Vol.11 No.4 p.338-359.
- 赤池 敏宏, 沓沢 好一, 荒津 史裕, Kakon Nag. バイオ人工肝臓へのチャレンジ - 革新的バイオマテリアルとしてのカドヘリンマトリックス工学の応用 -肝胆膵 70 (3) 375-384, 2015.